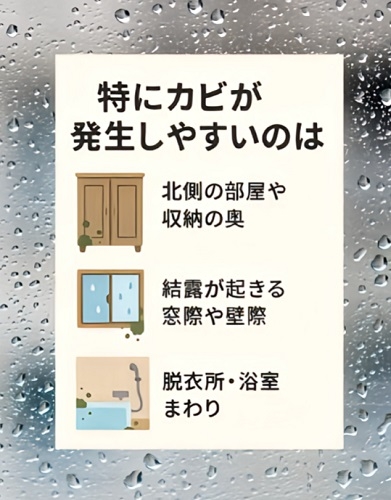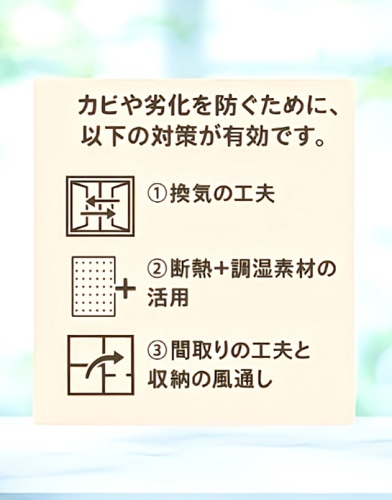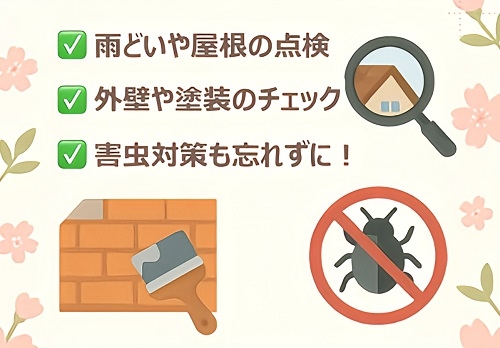本格的な台風シーズンが来る前に

連日、酷暑に見舞われていますが、
また一方で台風シーズンに突入していることも頭の片隅に覚えておきたいもの。
年々激しさを増す台風や、ゲリラ豪雨のニュースを見聞きする度に
「今年も備えなきゃ」と思いつつ、毎年同じような対策になっていませんか?
実は、台風への備えは"その場しのぎ"ではなく、"住まいそのもの"のあり方が重要です。
工務店の立場から見ると、台風に強い家づくりにはこんなポイントがあります。
①耐風等級の高い設計
建物の耐震性ばかりが注目されがちですが、
台風に備えるなら「耐風」性能にも目を向けましょう。
特に屋根・窓・外壁は風圧を受けやすく、
施工の質が住まいの安心を左右します。
②飛来物に強い窓まわり
シャッター付きサッシや強化ガラスの採用、
外付けブラインドなども台風対策に有効です。
実際、強風で飛んできた枝や看板で窓が割れる被害は少なくありません。
③屋根や外壁の定期点検
「うちは築10年以上だけど、大丈夫かな?」という方は要注意。
小さなひび割れや釘の浮きも、強風雨の前では大きなリスクになります。
点検やメンテナンスのご相談もお気軽にどうぞ。
④雨どい・排水の確認
見落としがちな雨どい。
落ち葉や土が詰まっていると、ゲリラ豪雨であふれ出し、
外壁の傷みや浸水被害の原因にも。点検は年1回が理想です。
私たちが目指すのは、「災害に強い住まい=日々の安心が続く家」
台風が来ても、家の窓を閉めたら、食事をしたり、休息したり、談笑したり...
そんな「いつもの暮らし」を守るために、住まいの備えは欠かせません。
特別なことではなく、"もしも"に備えた住まいの見直しを、この機会にしてみませんか?